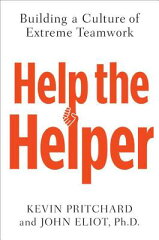10年勝ち続ける最強チームの作り方(ジョンエリオットさん・ケビンプリチャードさん)
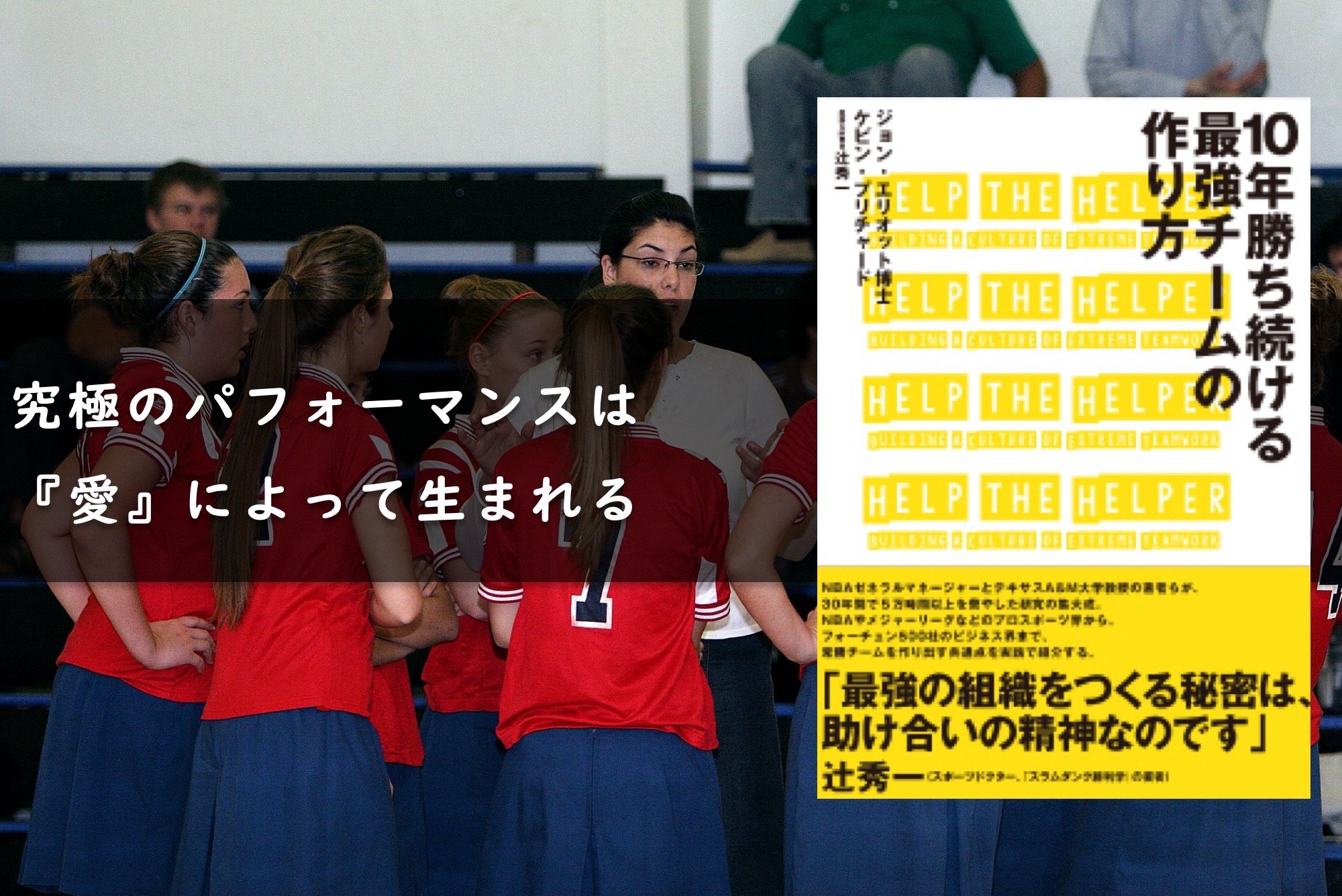
- 最強組織の秘訣
- 究極のチームワーク
- Chapter1 類稀なチーム
- Chapter2 無私無欲の王朝を築く
- Chapter3 ジャージの前面
- Chapter4 ムチを捨てよアメも捨てよ
- Chapter5 エネルギーを管理する
- Chapter6 30分ルールの行使
- Chapter7 真の精神力を持つ
- Chapter8 ”測定不可能”を測定する
- Chapter9 ”非”リーダーになる
NBAゼネラルマネージャーとテキサスA&M大学教授が5万時間以上費やした研究の集大成!
常勝チームを作り出す共通点を実話で紹介した一冊です!
Chapter 1 類稀なチーム
一次チームワーク:ヒーロー陶酔型チームワーク
人は、権力を持つリーダーに本能的に惹かれる
リーダーが好調なら組織は成功し、しかも大成功に至ることが多い。
しかし、リーダーに支払う目に見える報酬が高ければ高いほど、一次チームワークはますます巨額の負債になる。
二次チームワーク:戦術盲信型チームワーク
学識が全てに勝る。階層的な組織デザインとバイスプレジデントを柱とする。
二次チームワークの弊害として、ライス大学の学生のコメントが記述されていた。
「僕たちは〜(中略)〜複雑な作戦を全て暗記していますが、〜(中略)〜おそらく余計なものなんじゃないでしょうか。僕たちはライス大生ですから。頭じゃ誰にも負けません。でも、自分たちが本当に優秀な運動選手でもあることを忘れていると思います」
三次チームワーク:究極の助け合い型チームワーク
パフォーマンスの「真の源」
これまで述べられた一次チームワークと二次チームワークについての誤解を解くためにこうも述べている。
「大胆なリーダーシップも大胆な戦術も悪いわけではない。強烈なチームはどちらも優れている。優れたリーダーシップの資質とトレーニング方法を備えた人物。つまり、ロールモデルやコーチは必要。また、経験から引出され、じっくり寝られた戦術。つまり、自信を与える効率的なシステムも欠かせない。さらに、リーダーと戦術をよく吟味して、組織にとって有効に作用しているかどうかを検証しなければならない。」
そして、続けてこう述べている。
そこそこ平凡な企業から、ごく一握りの、本当に素晴らしい職場として際立つ企業へと飛躍する企業は、もう一歩先をいく。
経営の優先課題として、3次チームワーク(究極の助け合い型)を追求する。
最高のウェイターは自分の客を満足させて終わりではない。「たった今、何をすべきか。レストランのフロアを通り抜けている今この時、この空間を喜びで満たすために自分に今何ができるだろう?」
助けることを原動力にして、職場における日々の選択を行う。これは、暗黙の決まりであり、プライドである。これが、ヘルプ・ザ・ヘルパーのチームワークである。
Chapter 2 無私無欲の王朝を築く
ベンチにいる全員が完全に身を入れている
デューク大学のバスケットボールチームが毎年卓越した成績を残しているのにはこのような理由がある。
「一流選手や全米代表選手、最優秀選手を多数獲得しているからではない。チームの名声を決めるのは、ベンチの一番最後に座る選手であり、その選手があらゆる背景や状況で、どう振る舞い、どう反応するかによって決まるのである。」
Chapter4 ムチを捨てよ アメも捨てよ
私が最も印象に残った章は、この「ムチを捨てよ アメも捨てよ」だった。
この章は、ノーマン・シュワルツコフ元陸軍大将がダーデン経営大学院の訪問した際に、「部下にやる気を起こさせるには」というテーマで公演を行った話から始まる。
元陸軍大将でもある彼は「他人にやる気を出させることは誰にでもできる。〜 中略 〜 自分の身を危険に晒し、歯を食いしばり、打たれないように祈る程度の姿勢よりも、遥かに大きなものがなければ、数の上では劣勢の軍隊が勝算を覆し、絶体絶命の試練を切り抜ける道を見出すというような最適なパフォーマンスが発揮されることはない。それには並々ならぬ集中力と、断固たる決意と、明晰な思考が必要なのである。」
続けて彼は、こうも言った。
「それは誰かの頭に銃を突きつけて得られるものではない。そうゆうやり方では、明晰な思考”以外の”ものしか得られないことは、私たちの友人が今日ここで示してくれた通りだ。」と。
最後に彼はこう言った。
「戦争の目的は自由だ。 〜中略〜 本当の自由とは”愛“である。原動力となる愛を引き起こす方法を見つけない限り、あなたはリーダーとして失格だ。」
この本から伝わってきたものは、”愛”であった。
究極のパフォーマンスはお互いを思いやる気持ち。助け合い。
お金(サラリー)や結果を最終目的にするのではなく、友人への”愛”や家族への”愛”、チームへの”愛”、そして、競技への”愛”がここぞという時に発揮される。
メダルや称賛などの成果を求めるのではなく、精神的な理由からの動機付けへと移り変わることが「究極の目的」に届き始めるのではないでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
書籍情報
【日本語版】
ダイレクト出版 初版2017年8月10日
著者 ケビン・プリチャード
ジョン・エリオット
【英語版】
“Help the Helper: Building a Culture of Extreme Teamwork”
PORTFOLIO 2012
Kevin Pritchard, John Eliot